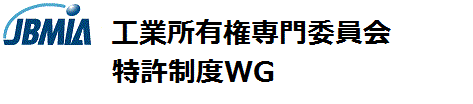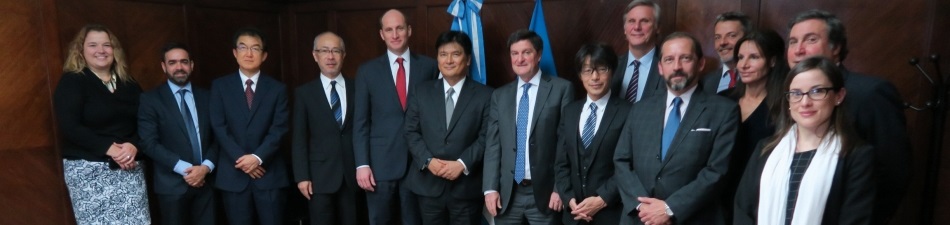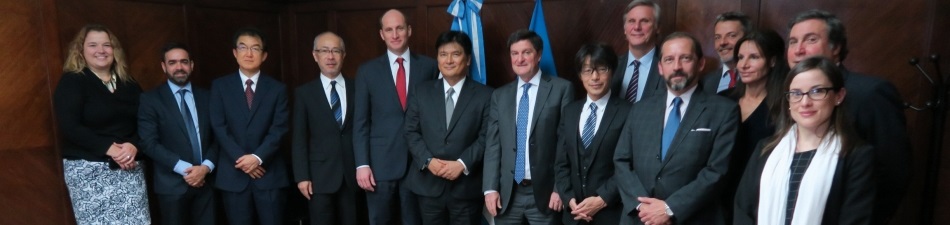| 年度 |
|
 |
 |
 |
|
・1994年度より |
1993年のコンピュータソフトウェア関連発明に関する審査基準について検討
→ソフトウェアによる情報処理自体が自然法則を利用している場合だけでなく、
情報処理自体が自然法則を利用していなくとも処理においてハードウェア資源が利用されているような場合には、
法上の「発明」として保護対象となる旨が明らかにされました。 |
|
 |
 |
 |
|
・1996年度4月 |
|
「ソフトウェア関連発明ガイドブック-審査基準から見た事例研究-」を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・1996年度 |
米国でのソフトウェア発明に対する改訂審査基準(MPEP)、その他資料、米国判例等の検討
→米国で媒体クレームの先駆けとなる審査基準が出されたことに伴い、その研究を行いました。 |
|
 |
 |
 |
|
・1997年度 |
|
 |
 |
 |
|
・1998年度 |
日本国内における「媒体クレームを含む特許」の出願案件の調査研究。
また日本でも米国と同様、媒体クレームに対応した審査基準改訂
(1997年:特定技術分野における審査に関する運用指針⇒コンピュータ・ソフトウェア関連発明で記録媒体を『物の発明』として
権利化を認める旨を明示しました)が開始され、その検討を行いました。
「平成10年度 ソフトウェア関連発明出願動向分析-ソフト特許分科会報告書-」を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・1999年度 |
|
ソフト関連発明に関する調査・研究の発展として、話題となったビジネスモデル特許に注目。
日米におけるこのビジネスモデル特許の出願並びに登録の実態について、多くの事例を抽出し分析を行いました。
「平成11年度 ビジネスモデル特許の動向分析-」を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・2000年度 |
|
プログラムクレームの研究、プログラムを認めた審査基準検討、プログラムクレームに対する仮想事例の検討開始、
さらに産業構造審議会での法改正検討報告の検討、法改正への対応 |
|
 |
 |
 |
|
・2002年度 |
「平成14年改正特許法の研究-ソフトウェア関連発明の視点から-」(2002年10月)を発行
「ビジネス特許関連発明と第29条第1項柱書違反について」(2003年5月)を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・2003年度 |
|
改正された「発明の単一性」の研究、及び各国比較について」(2004年6月)を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・2004年度 |
|
「補正制度・分割制度の見直し等についての考察・研究」(2005年1月)を発行 |
|
 |
 |
 |
|
・2005年度 |
「ビジネス特許関連発明と第29条第1項柱書違反について~その後~」(2006年7月)を発行
|
|
 |
 |
 |
|
・2006年度 |
|
 |
 |
 |
|
・2007年度 |
|
BRICsの特許制度を研究、BRICsの出願状況や特有の特許制度などを調査 |
|
 |
 |
 |
・2008~
2009年度 |
|
審査ハイウェイに関し検討、申請要件と実務上の手続き、利便性向上に向けた動向、事例を分析 |
|
 |
 |
 |
|
・2010年度 |
|
中国専利権侵害訴訟の実情を研究、中国での専利権侵害訴訟にあたって留意すべき事項を明確化 |
|
 |
 |
 |
|
・2011年度 |
|
中国実用新案の維持率と活用について研究、維持比率の高い要因、実用新案活用方法、事例を紹介 |
|
 |
 |
 |
|
・2012年度 |
|
複数国(日米欧中)出願時の留意点を研究、日米欧中における審査実務を調査し、複数国に出願する場合に有益となる情報を提供 |
|
 |
 |
 |
|
・2013年度 |
|
クラウド・ネットワーク特許に関し研究、ネットワーク・クラウド特許における複数主体/域外適用について、侵害判断の基準を検討し、
複数主体/域外適用が争点となる場合の侵害予測を可能とするための判断材料を提供 |
|
 |
 |
 |
|
・2014年度 |
|
損害賠償額の算定方法(クレーム記載とイ号製品における特許の寄与率の関係)に関し研究、
権利者から見た賠償額を高額化するためのクレーム・明細書の記載のあり方、被疑侵害者から見た高額な賠償請求に対する反論方法を検討 |
|
 |
 |
 |
|
・2015年度 |
|
日本の知財課題(審査基準・審査運用等)に関する検討を行い、特許庁と各企業における意思疎通に関する問題点に関して、
特許庁へ意見具申 |
|
 |
 |
 |
|
・2016年度 |
|
米国特許に関する現状分析を行い、審査の質に関して、法令・審査基準の観点、翻訳精度・クレームの書き方の観点から検討 |
|
 |
 |
 |
|
・2017年度 |
|
新時代技術(IoT)の特許権利化手法に関する研究を行い、またIoT関連出願の権利化手法に関して特許庁と意見交換 |
|
 |
 |
 |
|
・2018年度 |
|
事務機器分野におけるIoT関連出願の審査状況をZITに基づいて分析を行い、またZIT付与基準に対して特許庁と意見交換 |
|
 |
 |
 |
|
・2019年度 |
|
AIを利用した発明の権利取得、権利活用などに関する研究を行い、またAIを利用した発明の特許性について特許庁と意見交換 |
|
 |
 |
 |
|
・2020年度 |
|
①UP/UPCの権利化前後の費用面に着目した利用課題、②欧州におけるライセンスオブライトの主要参加国の制度比較および活用状況に関する研究を行い、また特許庁のCOVID-19施策やAI関連発明の出願状況調査結果について特許庁と意見交換 |
|
 |
 |
 |
|
・2021年度 |
|
通信技術を利用する立場での標準必須特許に関する調査・分析を行い、また口頭審理のオンライン化について特許庁と意見交換 |
|
 |
 |
 |
|
・2022年度 |
|
米国NPEに関する調査・分析を行い、NPEとの訴訟における防御手段のひとつであるInter partes review(IPR)の近年の傾向からIPR申立の際に取るべき対応を検討 |
|
 |
 |
 |